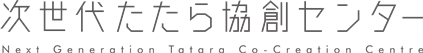公開日 2025年10月09日
和鋼博物館(安来市安来町)で2025年10月2日から4日まで古代たたら操業が行われました。内閣府地方大学・地域産業創生交付金事業「先端金属素材グローバル拠点の創出-Next Generation TATARA Project-」(令和5年から「展開枠」として採択)は、国内外の研究機関と企業が共創し「次世代たたら文化」を創造することを究極の目標としています。今回、事業の原点である「たたら製鉄」を経験しました。
古代たたらとは、公益財団法人日本美術刀剣保存協会が運営する日刀保たたら(奥出雲町大呂)で年3回行われている17世紀ごろに確立された舟形炉の永代たたら(1回の操業で約2.5t鉧製造)とは異なり、奈良時代ごろから行われていた巾奥行55cm程度の小型の炉によるもので、1回の操業で約数十kg鉧製造できます。株式会社プロテリアル技能養成員のほか、本学「たたらと現代製鋼」(會下和宏 総合博物館教授 主担当)履修生10名を含む一般参加者が、堀尾薫村下(ムラゲ)の指導の下、たたら製鉄に挑みました。1~2日目は、は炉の使用場所によって砂と粘土の配合が異なる構成のブロックを全員で作成したり、火力の強い松炭、広葉樹で炭化が不十分な固定炭素が少ない独特なたたら炭の大きさを整えたり、堀尾村下、佐藤村下代行の指示で築炉し、炉を乾燥させました。最終日はあいにくの天気でしたが、4時50分に火入れが始まり、早朝から、砂鉄・木炭をタイミングと量の指示に従って投入し、参加者が番子(バンコ)となって代わり替わりふいごで空気を送り込みました。15時30分ごろに鉧出しを行いました。今回は砂鉄を124㎏、木炭を183㎏使用して、30㎏強の鉧ができました。鉧の内部に良質な玉鋼ができているのか楽しみです。
歴史があり、高品質で文化的価値が高い鋼が生み出されるたたら製鉄を体験することは、高度で精緻な工程を伝わりやすい言葉で教えることを学び、多様性が目標達成の力になる瞬間を体感でき、産学連携で金属系新素材の研究開発を行うNEXTAにとっては貴重な気づきの機会となりました。


■和鋼博物館 館長 長谷川正人 様
日本刀の原料として使用されるたたら製鉄で生み出される玉鋼。日本刀の機能と工芸美を生み出すには欠かせないと言われています。多くの方の参加をいただき、たたら製鉄の魅力や苦労を直に体験いただける機会になったかと思います。
たたら製鉄は、一子相伝で伝えられたともいわれており、ベールに包まれた歴史、伝統、技術の奥深さを探索することは、科学や歴史に興味がある方を引き寄せるテーマでもあります。これらの魅力を今後も発信し続けたいと思います。
■公益財団法人日本美術刀剣保存協会 日刀保たたら 村下職 堀尾薫 様
日本古来の製鉄法「たたら製鉄」今回の規模は6世紀後半に製鉄が日本で始まったころのモデルとしました。先人が創意工夫し生み出された製鉄法を体験いただくことで人間力のすばらしさ、温故知新という言葉の通り「いにしえの技術を学び、そこから新しき知見を見す」ものづくりの原点から新技術を生み出していただければ幸いです。
■島根大学総合博物館 教授 會下和宏
授業の実習として参加した学生たちは、村下や株式会社プロテリアル担当者のご指導のもと、一生懸命、作業に取り組むことができました。モノ作りの難しさと大変さ、モノ作りに向き合う職人の真摯で真剣な姿勢について、体験を通じて学ぶことができました。また、一緒に参加していた株式会社プロテリアル技能養成員や他大学の学生とも交流することができ、良い刺激になったことと思います。
文責 NEXTA 柴田雅光